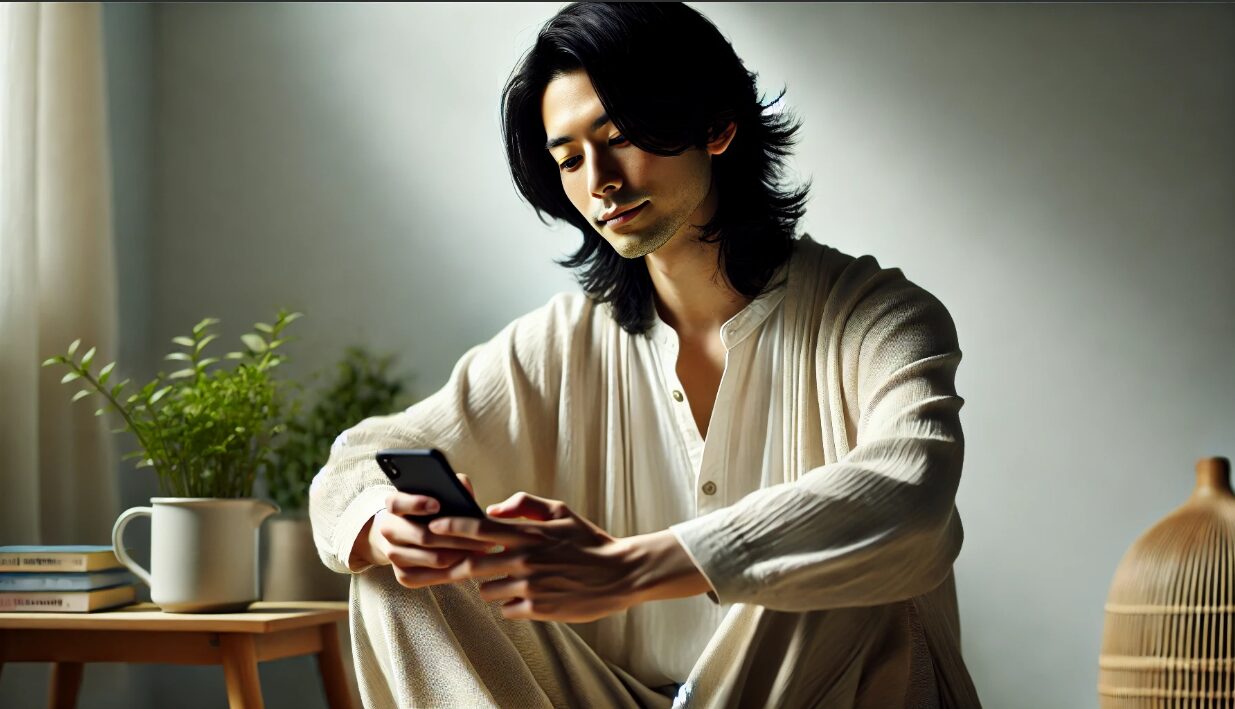
唯一無二の音楽性とミステリアスな雰囲気で、多くの人を魅了し続ける藤井風さん。彼のパフォーマンスや楽曲に触れるたび、そのジェンダーレスな魅力に惹きつけられますよね。
彼のジェンダーや恋愛観について、「実際のところどうなんだろう?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
特にインスタでの発言の真意や、graceやdamn、きらりといった楽曲の歌詞に込められた深い意味について、もっと知りたいと感じているかもしれません。
また、彼のファッションがなぜこれほどまでにジェンダーの壁を感じさせないのか、過去のNワード使用問題にどう向き合ったのかなど、彼の多面的な部分からその思想を探りたいと思うのは自然なことです。
この記事では、そうした疑問に答えるべく、藤井風さんの歌詞、インスタでの発言、ファッション、そして彼の哲学までを徹底的に掘り下げ、そのジェンダー観の核心に迫ります!
なぜ藤井風のジェンダーが注目されるのか?

藤井風さんのジェンダー観がなぜこれほどまでに話題になるのでしょうか。その背景には、彼の独特な存在感やファンを驚かせたインスタでの発言、そして何より彼の楽曲が持つ深い世界観があります。
ここでは、人々が彼のジェンダーに惹きつけられる理由を、具体的な発言や歌詞から探っていきます。
インスタの質問で明かした恋愛観
藤井風さんのジェンダー観が注目される大きなきっかけとなったのが、インスタグラムの質疑応答でした。
ファンからの「Are you gay?(ゲイなの?)」という非常にデリケートな質問に対し、彼は「I like girls, too. (女の子も好きだよ)」と返答したのです。
この回答のポイントは、「too(~も)」という一言です。これは「男性が好き」という可能性を否定せずに、「女性も好き」と付け加えることで、愛情の対象を特定の性に限定しない、彼の包括的な愛のスタンスを示唆しています。
多くの著名人がスルーしがちな質問にあえて誠実に答えた彼の姿勢は、多くのファンに感銘を与えました。この発言は、彼が自身のセクシュアリティを特定の枠にはめるのではなく、「全人類を愛している」という、より大きな愛の形を表現したものだと解釈されています。
ポイント
- 「女の子も好きだよ」という回答で、恋愛対象を限定しない姿勢を示した。
- デリケートな質問にも誠実に対応する人柄がうかがえる。
- 特定のカテゴリーに収まらない、普遍的な愛の価値観を持つ。
歌詞に込められたジェンダーレスな愛
藤井風さんの楽曲を聴いていると、自分の性別を意識することがほとんどありません。それは、彼の歌詞が一貫して特定のジェンダーに偏らず、「人間」という普遍的な存在に向けて歌われているからです。
彼の歌の登場人物や愛の対象は、性別が特定されていないことが多く、聴き手一人ひとりが自分自身の経験や感情を投影しやすくなっています。このジェンダーレスな表現こそが、彼の音楽が多くの人々の心に響く理由の一つと言えるでしょう。
graceの歌詞にみる自己愛の意味
楽曲「grace」は、彼のジェンダー観を理解する上で欠かせない一曲です。
この曲で歌われる「あなた」とは、恋愛対象の誰かではなく、自分自身の内側にいる完璧で神聖な自己、すなわち「ハイヤーセルフ」を指しています。
「助けて神様 私の中にいるなら」や「外の世界にずっと探してた真実はいつもこの胸の中」といった歌詞からも、愛や救いの源が自分自身の内にあるというメッセージが伝わってきます。
究極の愛を「自己との統合」として描くことで、他者との関係性で重要になる性別という概念そのものを超越しているのです。これは、最も根源的な愛は自分自身との間にあるという、彼の深い哲学を示しています。
damnの歌詞が示すセルフラブ
「damn」は、一聴すると執着的な恋愛を歌った曲に聞こえますが、藤井風さん自身はこの曲を「セルフラブソング」だと語っています。
この曲は、自分自身の不完全さやエゴと葛藤しながらも、最終的には自分を愛していくという物語です。特に注目したいのが、以下の英語詞です。
「i love me, and i will keep him in a safest fairest happiest place baby.」
公式 ミュージックビデオ「damn」
ここで自分自身の一部を「him」という男性代名詞で表現している点は非常に興味深いですよね。これは、理想の自己(ハイヤーセルフ)を男性的な存在として捉え、その存在を愛し守っていくという、複雑で深い自己愛の形を示唆しています。
単にジェンダーレスであるだけでなく、自己の内面でジェンダーの概念を柔軟に探求していることが、彼の表現の奥深さを物語っています。
きらりの歌詞と不特定な「君」
大ヒット曲「きらり」も、彼のジェンダーレスな世界観を象徴する一曲です。
この曲で歌われる愛情の対象は、最後まで「君」としか呼ばれません。この「君」は、恋人だけでなく、友人、家族、あるいは長年連れ添ったマネージャーなど、聴き手が自由に解釈できるようになっています。
「何のために戦おうとも動機は愛がいい」というフレーズに代表されるように、この曲の核心は、特定の誰かとの恋愛というよりも、人生を輝かせる普遍的な愛やつながりの尊さです。
性別を問わず、誰もが自分の大切な「君」を思い浮かべながら聴けるこの曲は、まさにラブソングの新しい形を提示していると言えるでしょう。
藤井風のジェンダー表現を多角的に分析

音楽だけでなく、彼のファッションやミュージックビデオ、そして社会的な出来事への対応からも、彼のジェンダー観や哲学が見えてきます。ここでは、さらに深く彼の表現を掘り下げていきましょう。
ファッションから見るジェンダーレスな姿勢
藤井風さんのファッションは、彼のジェンダーレスな表現において重要な役割を担っています。
彼は、ダークで両性的なデザインが特徴の「JULIUS」といったブランドとコラボしたり、アバンギャルドなデザイナーであるジャンポール・ゴルチエの服を好んで着用したりと、従来の男性的なファッションの枠にとらわれないスタイルを貫いています。
また、公式グッズのTシャツがユニセックスサイズで展開されているのも、ファンが性別を問わず一体感を共有できるようにという配慮の表れでしょう。
補足
彼のスタイルは、ライブでのオーガニックコットンを使った「リラックス&ネイチャー」な雰囲気から、「damn」のMVで見せたフリルのシャツにリーゼントといったハイファッションまで、非常に多彩です。
この振れ幅の広さが、固定的な男性像を押し付けない彼の姿勢を物語っています。
彼のファッションは、単に奇抜なだけでなく、穏やかさや内省といった内面的な価値観を表現する手段となっており、結果としてジェンダーの境界線を曖昧にしているのです。
燃えよの歌詞にみる自己肯定のメッセージ
「燃えよ」という楽曲は、直接的にジェンダーを歌ったものではありませんが、その根底に流れる自己肯定のメッセージは、彼のジェンダー観と深く結びついています。
この曲では、「クールなフリ もうええよ」「強がりも もうええよ」と、見栄や体裁を脱ぎ捨て、ありのままの自分を肯定することが歌われています。「もうええよ」という言葉には、諦めと許しの両方の意味が込められており、不完全な自分を受け入れる優しさが感じられます。
「明日なんか来ると思わずに燃えよ」という力強いフレーズは、世間の目や常識といったものにとらわれず、「今、この瞬間」を自分らしく生きることの大切さを教えてくれます。このような自己肯定の姿勢が、ジェンダーという社会的な規範からの解放にも繋がっているのではないでしょうか。
満ちてゆくの歌詞が描くスピリチュアルな愛
彼のジェンダー観を最も深いレベルで理解するには、「満ちてゆく」のような楽曲にみられるスピリチュアルな視点が不可欠です。
彼が大切にする「Prema」とは、見返りを求めない無私の愛、神聖な愛を意味します。この曲は、個人的な恋愛を超えて、生と死のサイクルや宇宙全体との一体感といった壮大なテーマを歌っています。
この哲学的な視点に立つと、ジェンダーを含む個人のアイデンティティは、一時的な器に過ぎないと捉えられます。最終的な目標は、個々の違いを超えて、より大きな存在と一つになることです。
彼の音楽がジェンダーを超越しているのは、ジェンダーを、スピリチュアルな悟りに至る過程で乗り越えるべき、この世的な概念の一つとして捉えているからなのです。
過去のNワード使用と彼の誠実な対応
彼の包括的な愛の哲学を語る上で、過去の「Nワード」使用に関する出来事も避けては通れません。
メジャーデビュー前、彼がYouTubeに投稿したカバー動画の中で、黒人差別用語である「Nワード」を含む歌詞をそのまま歌ってしまったことが、後に海外のファンから指摘されました。
注意:この問題はジェンダーに直接関わるものではありませんが、多様な価値観を持つグローバルなファンと彼がどう向き合っているかを示す重要な出来事です。
批判に対し、彼は迅速かつ真摯に謝罪しました。自身の「無知」が原因であったと全面的に非を認め、「二度と起こらない」と約束し、「学び続ける」と誓ったのです。
この潔く誠実な対応は、多くの人々に支持されました。過ちから逃げず、謙虚に学び成長しようとする彼の姿勢は、彼の音楽が持つ誠実さと一致しており、彼の哲学が単なるパフォーマンスではないことを証明しました。
まとめ:藤井風のジェンダー観が示す新時代

これまでの考察をまとめると、藤井風のジェンダー観は、彼を「ストレート」や「ゲイ」といった単一のレッテルで定義しようとすること自体が、彼の芸術の本質を見誤らせるという結論に至ります。
彼のジェンダーレスな表現は、彼が掲げる「Love All, Serve All(すべてを愛し、すべてに仕えよ)」という哲学から生まれた必然的なものです。それは、男性と女性という境界線だけでなく、自己と他者、聖と俗といったあらゆる壁を取り払おうとする試みです。
藤井風さんは、力強さや支配といった従来の男性像とは異なる、脆弱性、穏やかさ、そして自己受容に根差した「新しい男性性」を体現しています。彼の圧倒的な人気は、この新しい価値観が、時代に広く受け入れられていることの証と言えるでしょう。
最終的に、藤井風さんのジェンダーへのアプローチは、愛こそが最も重要なアイデンティティであり、性別は広大な人間の経験の中の一つの美しい側面に過ぎない、という新しい世界の扉を開いてくれるものなのです。





